箕輪厚介著、マガジンハウス、8月16日に読み始め、今日読了しました。
p6-9 編集者は最強だと感じる3つの理由がある。
1つ目は「才能カクテルが飲み放題」だから。(略)
2つ目は、「ストーリーを作れる」ということ。(略)
そして3つ目は「人の感情に対する嗅覚を磨ける」ということ。(略)
p9 編集者の根本は遊びのように仕事を、仕事のように遊びをやるということだ。
p29 編集者などという仕事は善悪や倫理など関係ない。自分の偏愛や熱狂が抑えきれなくなって、ほとばしって漏れ出したものが作品に乗って世に届くのだ。
p49 民衆は「正しい情報」よりも「楽しい情報」を求めている。これは江戸の瓦版のころからの真理だ。おもしろおかしく、刺激的な言葉を吐く講談師や噺家は、民衆から喝采を浴びる。「正しい情報」をありのままに伝えたところで、人々は幸せにはならない。そして「正義」ほど曖昧で、一方的で、暴走しやすいものはない。
p49 僕の周りには真の才能がいる。本当に日本を背負い変える覚悟と能力がある起業家やアーティストや作家、批評家がいる。
だからこそ僕の役割はギリギリのラインを歩きながら火を放っていくことだ。正義や真実は、新聞記者やジャーナリストが追求してくれればいい。「正しいことより楽しいことを」「過激にして愛嬌あり」。これこそ僕という編集者がなすべき仕事だと思っている。
p83 〇〇の営業マン。〇〇のデザイナー。なんでもいいが、〇〇というキャッチコピーが自分とその他大勢を分けるのだ。実力だけが分けるのでは決してない。
p88 そして気付いた。これって俺自身がインフルエンサーになれば最強なんじゃないのだろうか。物が溢れる時代。もはや物を選ぶこと自体に疲れる。自分が信頼する人のおススメを選ぶようになるのは時代の必然だ。インフルエンサーの力はどんどん強くなるに決まっている。
さらに、これから物を選ぶ基準は「物語」になる。安くて良い物は溢れている。だから、機能としてのTシャツはユニクロで十分だ。あえてTシャツを選び取る理由は、Tシャツのデザイナーの生き方が好きとか、何かメッセージを代弁しているとか、そこに込められた物語の部分、制作者の顔でしかない。
p88-89 特に本などのコンテンツは機能や値段では選ばない。その裏にどんな思いがあるか、誰が編集しているかまで込みで買うか決めるようになる。
TSUTAYAの映画コーナーが監督名でDVDを並べているように、これからは書店も編集者名で本を並べるようになるかもしれない。そう思った。
「箕輪さんが編集したなら買う」という存在になるしかないと考えた。
だからツイッターでは本の宣伝だけではなく、自分の人間性を丸出しにして、人生丸ごとさらけ出していくことに決めたのだ。箕輪の生き方が好きだ、共感する。だから彼が編集した本を読みたい。そうなるしかないと確信した。
p92 成功する企業には感情で動くアーティストと数字で動くサイエンティストがいると言われるが、アーティストが数字のことまで考え出しては、ビジネスは大きなものに昇華しない。これ絶対おもしろいからやりたい!という無邪気な人間と、でもそれって儲かるの?と言う冷静な人間の二人がいて、現実のプロジェクトは進み始める。
p92 「風呂敷広げ人」は何もしない。周りをワクワクさせ、巻き込むことができればいい。だから夢が大きいバカがいい。しかし、まだ何者でもない人間が大風呂敷を広げたところで、誰も畳みに来てはくれない。
「この人のプロジェクトに参加してみたい」「この風呂敷を畳む一人として、祭りに参加してみたい」。そう思わせる力がなければ、人は誰もついてきてくれない。
p93 「風呂敷広げ人」になりたければ、この人の風呂敷だったら畳みたい。今までの彼の行動から考えて、今回もかならず大きな夢を見られるはずだ、とワクワクさせることができないといけない。もはや人はお金では動かない。夢を見させられる言葉と実行力、そして何より本人が楽しそうにしていることが大切だ。
海賊船の船長のように、飲んだくれていてもいい。突如として「あの島に宝が眠っている」と叫び、こいつが言うのだったら多分本当に宝がある。たとえ、なくても楽しそうだと思わせることができるかどうか。トラブルはかぶる。この人のためなら集まろうとみんなに思ってもらえる人間かどうか。
風呂敷広げ人は何もしなくてもいい。目をキラキラさせて「宝がある」と叫べ! 乗組員に夢を見させる愉快な船長であれ。
p95 しかし誤解を恐れずに言えば、これからのビジネスはほとんどが宗教化していくと思っている。信者を集めることができなくてモノを売ることなどできない。
その背景は人が孤独になったことと、物質的に満たされたことの2つだ。
人はスマホによって孤独になった。スマホという小宇宙によって、人は自分が好きなものしか見ないようになった。その結果、好みや生き方が凄まじい勢いで細分化した。スマホから顔を上げると、周りは自分とは違う世界の住人ばかりだ。
テレビという画面の前に家族仲良く座っていた10年前のように、学校や会社に行けば昨夜のドラマの話題をみんなでするということはなくなった。今では同じ会社の隣の席の人でも、何が好きかどうかわからないというのが普通になった。
人は多様になった。悪いことではない。しかし、その結果として人は孤独になった。好きなものを語り合い、同じ想いを共有する場所がなくなったからだ。
そこで生まれてきたのがオンラインサロンをはじめとするネット上のコミュニティだ。会社や学校など物理的に近い人とのコミュニティが解体された一方で、SNSなどによって、同じ趣味や価値観を持つ人と、距離を超えて繋がりやすくなった。
p96-97 実現したい世界や大事にしている想いを表明し、共感する社員を集め、モノを作り、お客さんの支持を得る。
衣食住という最低限のものが満たされて豊かになると、人は物質的な価値ではなく、想いで動くようになる。
『モチベーション革命』(尾原和啓著)で紹介されているが、達成・快楽・没頭・良好な人間関係・意味合いという5つの欲望のうち、高度経済成長期の人はまえの2つ、今の30代以下はうしろの3つを重視している。分かりやすく言うと昔は金を稼いで高いワインで美女と乾杯するのが幸福だったのが、今は自分が意味を感じることを、好きな人たちと、ただ没頭することに幸福を感じるのだ。
p97 NewsPicks Booksも箕輪編集室も情報や物質を売っているわけではない、思想を売っているのだ。そこに共感する人たちが集まってコミュニティ化している。周りから見れば信者のように見えるかもしれないが、それは間違っていない。
ただ宗教と違うのは多様な意見が受け入れられて、出入りが自由だということだ。
もはや品質が良いものや安いものを作っても意味がない。そんなものはもう消費しきれないほど世の中にある。
実現したい世界や価値観を表明し、体現する。多くの批判と世間からの返り血を浴びながら、それでも共感してくれる人を集め、巻き込んでいく。そんな教祖力を持った人がこれからの時代を作っていくものだと思っている。
p102-103 よく、時代が変わっても変わらない普遍的なことを学ぶために一度下積みをしたほうがいい、就職はしたほうがいいと言う人がいる。
しかし、普遍的なことというのは現場で死に物狂いで試行錯誤していれば自然と身に付いている。学ぶものではない。特に今のような変化の速い時代では上の世代の成功体験は役に立たないどころか、視界をにごらせる時代錯誤の不純物にすらなる。
自分で手を動かし物を作って、人々のリアルな反応を見て一喜一憂しながら、成長していくのが一番手っ取り早い。つまり、いい組織とはチャンスが多く得られる組織だ。大企業でも球拾いのような仕事しか回ってこないのであれば、自分は成長していないと焦ったほうがいい。「箕輪編集室」はチャンスに満ち溢れているから、編集者やライターの経験がなかった人たちが落合陽一や宇野常寛の記事を作ってガンガン配信している。記事の反響を見ながらトライ&エラーを繰り返しているから驚くほど上達も速い。
p103 人の何十倍も努力しろ、と言うけれど、人間はみな平等に24時間しか持っていない。不眠不休で働いたとしても、時間で考えるとせいぜい人の2倍しか努力はできない。では、どこで差がつくか。それは「昨日までできなかったことをできるようにする」ということを日々積み重ねることだ。昨日と同じコピー取りを今日も繰り返していたところで成長はない。今はSNSでもオンラインサロンでもチャンスに触れる機会は5年前に比べ段違いに増えた。時間は有限だ。人はすぐ死ぬ。だから「今やれ」。
「昨日までできなかったこと」をやる。その実践を繰り返した先にプロフェッショナルがあるのだ。
p105 「スピードは熱を生み、量は質を生む」尊敬する週刊文春編集長・新谷学の言葉だ。
p105 普段ならあり得ないスピードで走り抜けることで書き手との間にものすごい熱が生まれる。そして、その熱によって本に魂が入るのだと思う。
p106 多くの人は「スピード相場」というものの洗脳にかかっている。
本は6か月。デザインは1週間。会議は1時間。長い間そうやってきたという理由だけで踏襲されている「スピード相場」だ。
僕は本は3か月で作り、デザインも2日くらいでお願いし、会議は立ち話にする。
メールの時候の挨拶なんか、なんの意味もない。年賀状も同様だ。しかし、暇な人間は思考停止したまま慣習を踏襲する。本当に忙しくすれば、無駄なことはどんどん切り捨てざるを得なくなる。本質的な仕事だけが残っていく。次第に生産性が上がっていく。
p107 また極限までに時間がない状況は人の集中力を飛躍的に上げる。
書籍のネームやタイトルは正解などないのだから締め切りがなければ永遠に考えることができる。しかし僕は打ち合わせの合間のタクシー移動中くらいしかネームを考える時間はない。タクシーの中で書籍のタイトル、帯のコピー、新聞広告のキャッチ、書店パネルの煽り文句を一気に考える。もっとじっくり考えたいとも思うが、時間をかければそれだけでいいものができるというわけではない。
いいタイトルなどは何週間も考えても思いつかず、もうタイムアップという瞬間に思いつくことがあると思う。
なぜなら集中力というのは、追い込まれた瞬間に最大値を記録するからだ。それならば、常に時間を区切って自分を追い込んだ状態にしておけば集中力は下がらない。
p109 表面張力ギリギリまでがんばっていたコップの水がザーッと外に溢れたあと、本当の能力が開発されるのだと。
p110 どうにか乗り越えられる量ではだめだ。それでは能力爆発は起こらない。絶対に無理、どんな方法を使っても不可能だというくらいの負荷を自分にかける。すると苦境を乗り越えようという防衛本能が芽生え、進化する。進化は危機からやってくるのだ。
p111 1年間で100の力が使えるとしたら、最初の2か月で90を使い切ってしまうくらいの気合いで走るといい。そこにインパクトが生まれる。圧倒的なまでに量をやるとキャパシティが増えて、また100の力がプラスされる。中途半端ではだめだ。
p111 そこそこ優秀。そこそこ目立っているうちは周りから可愛がられる。ずば抜けると評論家気取りの連中に、そのスタイルを批判、中傷をされる。
しかし、それがブランドになったという証拠だ。そして周りから批判を浴びたときに自分を支えてくれるのも、また量だ。「オレはお前らが寝てる間も動いている。誰よりも量をこなしてきた。舐めるなよ」と、確かな感覚が手に残っていれば、胸を張って戦える。
量だけは裏切らない。誰よりも動け。
p113 熱狂できることに出会うためには、自然消滅上等であれこれ手を出せばいい。
p113-114 「やりたいです」「考えます」などと言っている悠長な奴に黄金の果実は降ってこない。誰もそんな人間に渾身の企画を提案しようとは思わない。この企画は誰に相談しようと考えたときに、すぐに頭に思い浮かぶ存在でなければ編集者として失格だ。
p115 無責任とは僕に言わせれば熱狂してないのに業務的に仕事をこなしている状態だ。熱狂しているプロジェクトであればどんな困難が襲っても血だらけになりながら最後までやり切れるはずだ。集中力が違う。
しかし熱狂の種などまずはやってみないと見つからないのだ。だからこそ自然消滅上等で、片っ端から「やります!」と手を挙げていけ。あれこれ手を出しているうちに、好奇心を呼び、熱狂が熱狂を加速させる。
p118 多動力の本質は、あれこれ手を出すことではない。まず何か一つで突き抜けるということだ。なにか一つのジャンルで日本のトップになるから、横展開が可能になるのだ。何かのトップだから他のトップから声がかかるのだ。
僕だって誰よりも本を出している。誰よりもスマホを手から離さない。ずっと本のことを考え、寝ても覚めてもスマホの中でいかに展開するか企てている。だからこそ、いま編集とネットを組み合わせるのは日本で箕輪が一番得意だ、と思われるし、超重要案件の会議に呼ばれる。本とは関係ないプロジェクトでも仕事を頼まれる。そこで新しいプロジェクトが動き出す。各業界トップ・オブ・トップと仕事で交わることが許される。トップを目指すものだけが持っている苦しみと熱量、そしてアイデアを共有している人同士は、たとえジャンルが違っても、分かり合える。
p122 落合陽一の言葉に「変わり続けることをやめない」というのがある。人は変わることをやめたときに腐る。変わり方はこの際、いいだろう。
「変わり続けることをやめない」という意思を持ち続けられるかどうかがまず問われるのだ。
p123 しかし我々は食うためにやっていない。ただ楽しいから波に乗っている。しかし変化を楽しみ自由に舟を動かすほうが結果として財宝も見つけてしまうのだ。会社という大型客船よりも僕のこのゴムボートのほうが強いと確信している。
p127 編集者の仕事をしていくならば、全身ハリセンボンのように神経質で難しい起業家や作家、感受性をむき出しにして仕事をしている芸能人やクリエイターを口説き落として、親友、戦友、悪友のような、剥き出しで付き合える仲にならないといけない。
p128 こちらがガードを上げていれば、向かい合う相手も同じ高さでガードを上げる。こちらがガードを下げていれば、向かい合う相手もガードを下げる。自分がフル装備の完璧人間を装っていては、相手も装備を解除してくれない。
編集者という仕事は、書き手をどこまで丸裸にできるかが勝負だ。表面上の付き合いからは本物の言葉は引き出せないし、偽モノの言葉を紡いでも、ありきたりなコンテンツになってしまう。
そして、相手に装備を解除させ丸裸にするためには、まずこちらが、そこまで脱いでしまって大丈夫なのかと心配されるくらい、無防備になることが大事だ。
p129 この人と話しているときは一番自分らしくいられる、と思われるかどうか。
いつも小難しい話をしている人も少年のように無邪気なことを言い、いつも怖い顔をしている人も無防備でとろけた顔になる。そこまでできるかがサラリーマン的編集者と、本物の人間関係を築く編集者を分ける。
しかし、これは編集という仕事に限らない。営業だろうが接客だろうがコンサルティングだろうが、機械的な人間関係を突破し、相手の生身の感情を引き出し受け止め、溶け合うような関係になれれば、仕事は一気に加速し、本質的なものに変わる。
そのためにはまず自分から裸になってしまうことだ。自分の恥ずかしい部分も醜い性格もわがままさも生意気さも全部出してしまう。嫌われることなど怖れるな。全てを見せて嫌われるなら、それまでだ。大丈夫、完璧な人間なんてどこにもいない。
まずはこっちから全てをさらけ出してしまえば、相手も警戒を解いてこいつは信頼できると思ってくれる。丸裸になろう。
p131 仕事とはどこまでいっても人間と人間がやるものだ。
p133 相手が何を求めているのか、どんな本性なのかを、相手自身が気付いていないところまで想像し、理解し言語化することができれば、なんの実績もなくても信頼を勝ち取ることができる。
そうなって初めて人間と人間として信頼してもらえるのだ。
相手が自分に憑依してくるまで、想像して想像し尽くせ。
p136-137 絶対に言ってはいけない秘密なのに、「この人に言ってしまいたい」と思われる人間になれるかどうかが編集者として重要だ。僕は口が軽くて有名だが、日本中のタレコミ情報が集まってくる。形式的な仕事をしている人間に人は心を開かない。
僕にとっての目的は、あくまで良い作品を作って売ることであって、いくら著者のことが好きであっても、気に入られることは目的にはならない。だから僕は、怒られるかもしれないと考えて何かを躊躇することはない。作品が良くなるのなら言いにくいことも言う。それは、その瞬間嫌われても、売れればいいと思っている。地雷を踏みながらでも、ゴールまで駆け抜けてやるみたいな感覚。委縮することもない。
なぜなら、いくら良好な関係だったとしても、まったく本が売れなかったらお互いにもう一緒に仕事しないからだ。そこはシビアだ。ビジネスというのは友達ごっことは違う。結果と結果、力と力で向き合うしかない。しっかりと自分が思うことを伝え、良い作品に仕上げる。それが売れれば、その過程でどんなに「こいつ、図々しいな」と思われても、評価は一気に逆転する。編集者と著者の関係を超えていく。
p137 他にも数限りなく、本を作ったあとに本を超えて繋がっている。それは僕が著者の顔色ではなく目的を見ているからだ。結果が出ないいい人より、強引にでも結果を出す変態に仕事は集まる。
p143 あくまで自分が熱狂できるかどうか。世界中の誰も興味持たなくても、もし自分が最高の本だと思えれば僕はそれでいい。死ぬときに自分の編集した本を本棚に並べて、ときめくことができればそれが成功だ。本なんて売れなくても誰も死なない。会社がちょっと損するだけだ。大切なのは自分の心がどれだけ動くか。だから僕はただひたすらに自分の感覚で自分が読みたいものを作る。こっちから読者や時代に合わせに行くことはない。
p150 つまり「多動力」の本質とは「不動力」。
自分にしかできないこと以外は周りにふりまくる力のことだ。
こういった著者が発するメッセージの本質は、よほど読解力があるか、切実な問題として読書をしていないと見抜けない。
しかし本を編集していると文章の中に1文字でも腑に落ちないところがあると気持ちが悪くて、出版したくなくなる。一文字一文字を身体に染み込ませるようによく考える。真剣に言葉と向き合っていくから、言葉の裏にある著者自身でさえも言語化できていない真理が見抜ける。
p151 周りが引くくらい著者と本に没入する。誰よりも感銘を受け、実行し、自ら本の化身となりながら、その本のメッセージを生き方をもって体現する。言葉の羅列を見せるだけでは人は動かない。僕自身が誰よりも原稿に入れ込んでいるから読者も熱狂してくれるのだ。
p154 本にはいまだに幻想がある。本を書く人は先生で立派な人だ、というのはまだ崩れていない。でも僕は本を書きたいと思っている人に本を書いてほしいとは思わない。目の前の仕事に熱狂し、本なんて書く時間のない人を強引に口説いて本を書かせたい。
p155 出版人も自分たちは何か高尚なことをしているという自負を持ちながら働いていた。それ自体は悪いことではない。しかし、今や活字による情報やノウハウなどスマホがあれば無料で手に入るし、反対に出版社など通さなくてもツイッターやブログで誰もが世界中に活字コンテンツを発信できるようになった。
p155 僕は究極、中身がすべて白紙の本であっても、人の行動を変えることができればいいと思っている。情報の価値自体がかぎりなく0円になっている今、本は体験を売るしかない。
この本で意識が変わる、見方が変わる、行動が変わる。これらの体験までデザインすることが重要だ。
p155 僕はNewsPicks Bookで情報を売っているのではない。思想を売っている。そのあとのイベントやSNSでのフォローで体験をデザインし、行動を変えるとこまで考えている。評論家が☆1を付けようがどうでもいい。
p162 「努力は夢中に勝てない」という方程式は、編集者に限らずすべての仕事に共通する。目の前のことにどれだけ夢中になれるか。熱狂できるか。夢中の前ではどんな戦略もノウハウも無力だ。
p162 政府が一律で国民にお金を配るベーシックインカムの導入が各国で議論されている。
ベーシックインカム導入までどれくらいの時間がかかるかは分からないが、稼ぐために働くという生き方が減っていくのは間違いない。AIが発達し、農作業も配送業もロボットが寝ずにやるようになる。すると圧倒的に生産コストが下がる。月額いくらか払えば衣食住が保証されるサービスをフェイスブックやアマゾン、ZOZOが始めてもおかしくない。労働の時間は減り、お金の価値は下がり、やりがいや生きがいの価値が上がっていく。
p162-163 一億総老後時代のように、自分が人生をかけるほど好きなものを皆が探すようになる。今まではお金を稼ぐのが上手な人が豊かであったが、これからは夢中になれるものを見つけている人が豊かになる。儲からなくても夢中な何かがある人は幸福で、お金はあっても何をしたらいいか分からない人は苦しくなる。
p163 自分が夢中になるものを見つけるためには行動するしかない。
ウダウダと考えすぎずに、どんな仕事や誘いでも「やります」「行きます」を口癖にして、とにかく働く。そして小さな成功体験を重ねる。人は全く手の届かないものをほしいとは思えない。小さくても出来ることを繰り返していると、人生をかけて夢中になれることがやがて見つかる。
人生とはそもそも、自分が夢中になるものを探す旅なのだから、人生を賭けるほど夢中になれるものを見つけることは簡単ではない。
大切なのは常識に縛られないこと。個体としての欲望と偏愛を解放しろ。ごちゃごちゃ言う前にとにかく動け。
リスクと思っていることは全部、仮想的なものだ。人生など長いドラマであり、ロールプレイングゲームに過ぎない。失敗もトラブルも全部、話をおもしろくするためのイベントだ。
今ほど挑戦する人が楽しい時代はない。死ぬこと以外かすり傷と叫びながら、ただ狂え。
p165 「なんか今、もの凄い大きな音がしたけど、どっかで爆発でも起きたのか?」と思われるような、不確かで、何の意味もなく、解釈のしようがない存在でいいと思っている。そこに正義感や高尚な理念などない。時代のあだ花でいい。どっかで破滅して、なんか箕輪っていう編集者いたよねって言われるくらいがちょうどいい。
p166 破壊願望や破滅願望があって、安定してくると無性にその現状を壊したくなる。
p167 熱狂から持続のフェーズへ。さらに大きくスケールするうえでの間違いのないプロセスだ。
p167 しかし、僕自身は、落ちるか落ちないかギリギリの綱の上でこそ輝く人間だと思っている。動き続け、変わり続けないと飽きてしまう。僕が飽きていることは読者にはすぐにはバレないだろう。しかし、半年くらいのタイムラグがあって世間にもきっと伝わる。そうやって、多くのムーブメントが終わっていく。
p168 幻冬舎の若手編集者、NewsPicks Book編集長という最高に居心地の良い立場を変えなくてはいけないと思っている。違う時間軸で、今までではできなかった発想とスケールの仕事をして、その経験を幻冬舎とNewsPicksでの仕事にまた大きく戻したいと思っている。変わり続けることをやめた時点で、僕という人間に価値はない。
p168 だから、活動の領域を変えていく。本は本のままでは意味がない。本の中で世の中を変えようと訴えるだけではなく、僕自身が手を動かして世の中を変えていく。
p169 僕の編集する本は他のビジネス書とは違う。情報価値を重視していない。時代の爆発を捉え、今を生きる起業家のリアルなひとコマをカメラでおさえるかのように切り取り、ビタミン剤のように気合いを注入する。著者は変わっても大体パターンは決まっている。
なぜなら情報はどこにでもあるからだ。NewsPicksでもツイッターでも講演会でも、最先端の情報は、その意志さえあれば誰でも手に入る。日本を動かすような起業家と大学生に、得られる情報自体は大差がない。
p169 大事なことは、行動するかどうかだ。それだけで道を分ける。
落合陽一も前田裕二も佐藤航陽も毎日誰よりも行動している。他の30代と持っている情報や知識が違うのではない。命を燃やしながら走っているのだ。
p169 だから僕は、行動せよと読者の背中を押す。本はそのためのツールでしかない。
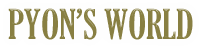
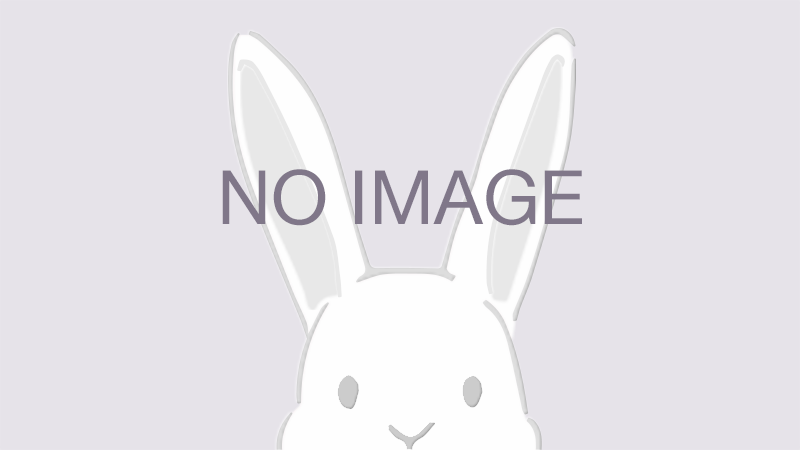

コメント