吉川雅之・倉田徹編著、明石書店、2017年8月10日に読み始め、7月15日に読了しました。
p3 「何故香港なのか」という学生からの問いに対して、「日本を相対化して見る上で最も恰好な社会だから」と答えたことがある。現今の諸問題や将来像まで含めた日本社会を再考するための鏡、という意味である。政治体制や経済水準、そして文化基盤が明らかに異なる社会を基点として日本を云々することは容易い。ならば、政治・経済・文化ともに共通点の多い社会から日本を問い直した場合、どうであろうか。その(難度の高い)問い直し、つまり己の社会を映し出すための鏡として、香港ほど有効に機能する社会を筆者は寡聞にして知らない。
p4 しかしそれでも、第二次世界大戦の3年8カ月を除いて香港と日本の間には支配関係が生じたことはない(この点で台湾とは異なる)。それにも拘わらず共通点の多い香港を基点として日本を見つめ直すことを、発想の転換も含め、お勧めしたい。本書はそのいざないである。
p182 ここまで見ると、文化の伝達は単なる「発信から受容まで」の一直線の過程ではなく、「誤配」を含む「二次創作の連鎖」と形容するのがより妥当であろう。
p197 1997年7月の香港返還後も、ムスリム人口は増え続けているという。多様な文化的背景を持つムスリムが香港に暮らし、独自の文化を育んできたという事実は、新しいシルクロードの名にふさわしい、香港社会の開放性や懐の深さを物語っている。
p206 数年前ある日系企業の香港支店長が「香港駐在は人生のボーナス」と、離任の挨拶をした。「確かにそうだ」と、しばらく香港にいる日本人の間で話題になった。商都香港はダイナミックで、自由度が高く、食文化が豊かで、余暇も充実、学校制度がしっかりしていて、日本にも近く、暮らしやすいとされている。
p209 一旦そのカードが手に入れば、労働ビザは不要となり、転職は自由だ。また香港は外国人の起業も歓迎している。
p247 香港の大学がこれほどまでに、国際競争力があるのは、なぜだろう? それは、現在の大学の形が、イギリス統治の最後の10年間に、頭脳流失を止めるシステムとして発展したからだ。返還後の明るい未来のために、地元で人材を育てようと、去り行く香港総督が残した置き土産とも言える。
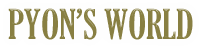
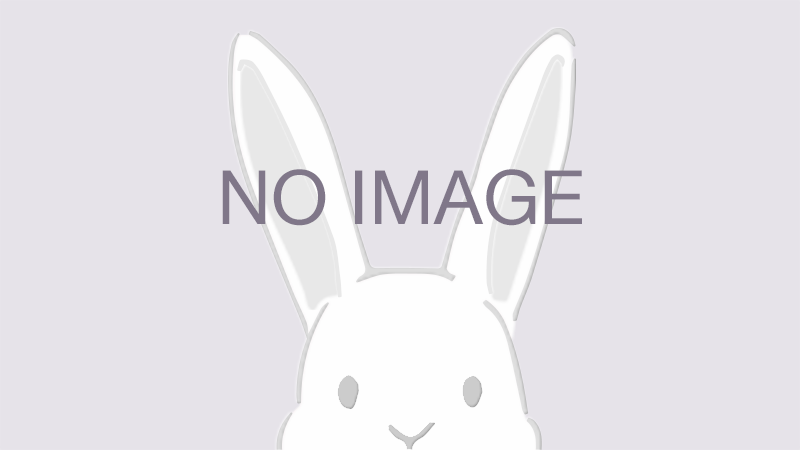

コメント