堂目卓生著、中公新書、9月16日に読み始め、9月25日に読了しました。
「言いかえれば、社会秩序を導く人間本性は何であろうか。『道徳感情論』において、スミスは、この問題に答えようとする。
したがって、スミスが容認したのは、正義感によって制御された野心であると結論づけられる。それはフェア・プレイのルールを守ること、胸中の公平な観察者が認めない競争を避けること、「徳への道」と「財産への道」を同時に歩むことであるともいえる。これらは、すべて同じことを意味する。スミスにとって、正義感によって制御された野心、および、そのもとで行われる競争だけが社会の秩序と繁栄をもたらすのである。
『道徳感情論』におけるスミスの問題意識は、ひとつの社会における秩序にかぎられるものではなく、社会と社会の間、あるいは国と国の間における秩序にも及んでいる。
しかしながら、分業による生産量の増大が実現するためには、生産に必要な、より多くの材料が前もって用意されていなければならない。たとえば、ピンの生産が増えるためには、より多くの針金がなければならない。また、分業によって、各業務で使われる道具や機械の種類と数量が増えるので、分業の効果を十分に引き出すためには、道具や機械も前もって用意されていなければならない。このことは、社会的な分業についてもあてはまるであろう。したがって、社会全体の生産物が構成員を養うだけで精一杯である状態では、分業は起こらないであろう。分業が可能になるためには、社会の構成員を養うのに必要な生産物を上回る生産物、つまり剰余生産物が存在し、蓄積されていなければならない。
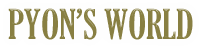
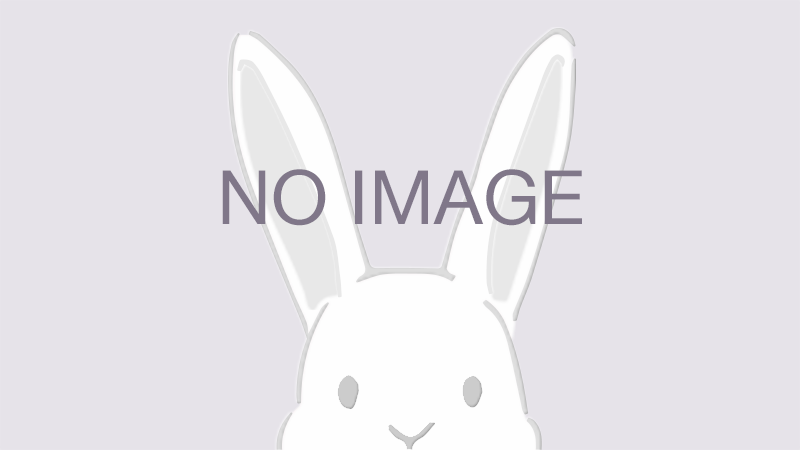


コメント