鈴木康之著、日本経済新聞出版社、10月21日から読み始め、12月12日に読了しました。
p4 ゆっくり読んでください。日常、新聞やポスターを前にしたときの一読者としてのようにさっと読んではいけません。テレビやラジオの一視聴者としてのように気楽に読んではいけません。
ひと噛みごとに噛み砕くように注意深く読んでください。
そして、勉強する者らしく繰り返し繰り返し読んでください。
この本によって、書き手の広告にせよ、新聞記事や番組にせよ、言葉をゆっくり注意深く探りながら吟味し、書き手の技を吸収する職業習慣を身につけてください。
そうした読み手、聞き手のプロフェッショナルとしての姿勢ができあがってはじめて、書き手のプロフェッショナルになっていくことができます。
p39 つぎの行へ、つぎの行へと誘っていかなければならないのがコピーです。その誘引力となるものが、メッセージ内容そのものの魅力だけでなく、つぎの行への期待感、つきあっていきたいと思わせる気持ちです。
p49 読んでもらう文章を書くことは、読む人の気持ちとのゲームです。巧みに書かれた文章は「え、なんだって」「なるほどね」という反応を読み手の中に引き出します。このことは文章を書くときの自己チェックになります。読み手の顔つきを想像して、どう反応するか、これでいいかどうか、用心深くよーくチェックしながら書き進めてください。
そういう反応が引き出せないと、読み手は文章から離れます。マイクのコードを引っこ抜かれます。ゲームオーバーです。
p49 コピーは人間を描きます。人の幸せ描写の域に至ったものが名作コピーなのかもしれません。
p50 コピーライターは読書が好きです。日本の文字そのものが好きです。言葉が好きです。本来人間みんなそうであるはずなのです。言葉で人とつきあい、言葉で生きているのですから。誤解を恐れずに言うと、人間、言葉でなんでもできる。恋も仕事もスポーツも言葉でできる。科学も信仰も、言葉です。仕事の質も効率も、社会や世界の動きも、当然歴史の流れも、変えるのは言葉で、です。先人たちはそうやってきました。
p59 コピーライティングの基本は、広告主から聞いてきたいい話のお取り次ぎなのです。いい話を聞けばいいコピーが書けました。逆にいえば、いい話を聞きだすまではいいコピーを書ける自信が湧いてきませんでした。
p69 そして、ここに新たな条項をひとつ、加えたい。
(第6条) スポーツマンは、ころんだら、起きればよい。失敗しても成功するまでやればよい。
p80 ヒアリングでは心も頭もまっさらにしていい聞き手になりなさい。全身全感覚でテープレコーダーになりなさい。実際にテープレコーダーも使いなさい。メモもだいじですけれど、メモのデメリットを恐れなさい。目をノートに向けている間、耳がおろそかになります。あなたの目が話し手の目から離れます。その間、話し手のだいじな何かを見落とします。
p80 いい話が聞けるまで、聞きなさい、待ちなさい。ぜひだれかに聞かせたい、という強い衝動に駆られるまで待ちなさい。いい話の中身だけでなく、その人独特の言葉遣い、クセやナマリ、息遣いまでも、土産として持ち帰りなさい。
p87 映像を見せながら、映像では表わせない世界を、名ナレーターが名ライターの台本を語り続けている、そんな思いの仕上がりです。(略)
言うまでもなく読む人を楽しませるための書き方なのですが、こういう作品を読んでいると、じつは書いている本人がいちばん楽しんでいるのではないかと思えませんか。
そうなんです、いちばんは本人なんです。本人が楽しいんでいないと、読み手にそれが伝わりません。土産話は、楽しみ方まで聞き手からのおすそ分けなのです。
p90 読んでもらいたいという衝動。この、タネやシカケになる、いいものを聞き質して見つけたとき、聞き手であり、つぎのステップでは書き手になる者の心に、ある感慨が生まれるわけですね。「それはいい話だ」「それは面白い話だ」「それはあの人にとってだいじな話だ」と気持ちが高揚する感動です。
それを文章にしたいという意欲の湧き出ずるのをいかんともしがたくなるのが、コミュニケーターとしての性です。その思いの高まりがコピーを執拗に磨き上げ、仕上げていく作業のエネルギーになるのです。
p91~92 コピーづくり、広告づくりという仕事に取り組もうとする私たちの目の前には、「チェルカ・トローヴァ」のメッセージがあるはずなんです。そして、探せば、思わず喜びの声が出てしまうような名コピーを発見できるはずなんです。
名コピーライターたちの名コピーは、仕事に取り組んだ当初にすぐ浮かんだものではないはずです。探して探して、探し求め続けて、発見できたコピーなんです。あったんです。
創造したものではないんです。
新語のような新しい言葉を作り出そうというのではありません。すでにあなたのまわりにある言葉の中から見つけ出すだけの作業です。もし見つからないようなら辞書を開いてごらんなさい。よりよい言葉、よりよい表現は陰に隠れていると思ってください。
なにかをどかせば次々に現われます。簡単には満足しないでください。天才ではなくて、努力家なのですから。もっと探せばもっといい言葉が見つかります。
いい言葉を見つけられ、いい表現で文章が決まったときの喜びは、一度経験したら病みつきになります。また見つかるはずだ、と。
ないはずはないんです。ないとは言えないんです。チェルカ・トローヴァ!
p95 (略)「文学の読書ってつまるところ人間観察、生活観察だよ」と言っていました。人間を読むための糧になる、暮らしを語るための糧になる、という意味でした。
p122 玉山さんは私に本音を聞かせてくれました。「一発で百点満点の完成品に到達することなどできるわけがない、というのが正直なところです。これが絶対正解だというのはないですから。毎日毎日考えて、何度も何通りにも書き換えて、締め切り時間がきたら、もうこの時点ではこれでいいんだろうか、という不安なまま手放しているっていうところがありますね」。
私もそういう仕事の仕方を流儀にしてきました。若い人たちにもそうしなさいと教えています。玉山さんは「原稿を提出して、そこから先はもう考えないというのは、コピーライターとしては怠慢です。OKが出たからおしまいなのでなく、入稿するギリギリまで一生懸命考え続けます。それが広告主さんへの誠意なので」と言いました。それは自分自身への誠意でもあります。
p162 思いは人さまざまです。しかも、思いのコピーライティングにはコピーライターに自由を与えます。自由であればあるほどコピーライターの小宇宙が個別化するでしょう。コピーライター自身の人間性や価値観が勝負を決めます。
p168~169 自分のことはなんにも分かっていない、というのがなにごとにつけ私の基本です。ましてや人のことなんかなにも分かるはずがない。けれども便宜上やむを得ず分かっている顔をしている。人もみんなたぶん自分のことを分かっていない。人もみんな分かっている顔をしているだけで、ほんとうは分かっていないはずだ。分かっていない者同士の世の中。分かっている顔している者同士の世の中。そう思います。
p171 分かっていない者同士なのだという前提に立つことがすべてのコミュニケーションの原点ではないかと思います。そこで機能するのが、単純で易しく、親切で優しい説明です。これが、分かってるよ、アナタ分かったでしょ、はい分かったね、という大ざっぱな気持ちでは説明になりません。
p186 磯島さんは「形容詞は少なければ少ないほどきれいです。なるべく具体的な説明をしたかった」と言っています。
p198 広告のようなコミュニケーションの場合は書き手が自信過多になることは反目的的です。写真の表現力のほうが勝るなら写真に、数字や仕組みの図による説明力のほうが勝るなら、数字や図に頼るべきです。
p234 コピーを書くということは、それを読んでくれる人とのゲームです。ずばりトクする情報、ソンする警告だけでなく、「なるほどもっともだ、それは道理だ」と納得させる言葉も人を捉えます。ボディコピーの一行一行もその連鎖でなければなりません。興味を失った途端、読む人はその文章から離れてしまいますから。
p316 (略)人間関係という絡みの中で人間を観察すると、勉強はどこまでも広がっていきます。一個人でも不思議な存在なのに不思議と不思議の掛け算になるのですから、万華鏡を覗くように面白い眺めになります。
p322 商品特性を理解してもらうことによってではなく、商品イメージを抱いてもらうことで差別化し、購買動機にする商品が多い時代です。ですから今日は面白さで感性訴求する広告が盛んです。CM媒体は面白さ訴求が得意です。しかし広告は面白さ訴求だけでは用が足りません。好感度の競争なのです。
p328~329 この項のはじめに「好感度」に触れました。好きになること、好きになってもらうこと。佐々木さんや福里さんたちが、なによりもだいじにしている広告観なのではないかと思います。理屈の上では当たり前のことなのですが、こうもつぎつぎと愉快な広告を発信する姿をよくよく考えると、善人クリエイターなんですね。現実にはいろいろ悩ましいことがあるはずなのに、ポジティブの限りを尽くしています。
広告とは世の中を面白いことで彩る仕事だ、そう考えているように思えて、楽しくなります。笑顔の国民運動を実践しているような、ちょっと気張って言うと、もう立派な社会貢献のように思えて来るんですね。たかが広告と言ってしまっては、当たらないようです。
そういう世界にいるという気概をもって、あなたも善人になってください。
p348 コピーライターやCMプランナーに限らないことですが、優れた表現者は内部に蓄えたもの、備えているものの質量が並ではありません。さる高名な建築家は若い世代に、とにかく古今東西の建築物、建造物をじっくり見なさい、大樹も山岳も星空さえも、と教えています。またさる写真家は、カメラを向けたくなったらシャッターボタンを押し続けなさい、丸一日でも、次の季節になっても、一年後でも、体調のいい日も悪い日も、と教えています。
表現者にはすべての経験がストックになるんです。
コピーライターにとってのストックとはなんでしょうか。積極的な実体験? 読書体験? 映画体験? 想像体験?……。
p377 まさにこの小説がそうであるように、手紙は書き手と読み手のゲームです。書き手が意図することをちゃんと読み取ってもらうコピーも然り。いやコピーにかぎらずあらゆる実用文は、読み手の心との一字、一句、一行、一文のゲームです。下手に書けば書き手も負け、下手に読めば読み手の負け。両者とも負けにならないのが、このゲームの理想型です。
ボールを投げたり捕ったりすることを投げっこというでしょう。ところが英語ではピッチボールとは言わないで、キャッチボールと言いますね。聞いた話ですが、相手が捕球しやすいように投球する遊びなんだそうです。野球の指導書には、投球の最初から最後までボールを受ける相手や的とするグローブの位置から目を逸らさずに投げること、と書いてあります。コピーのようなコミュニケーションのことを言い得ていて妙です。それは日常の会話でもそうではありませんか。
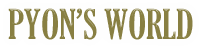
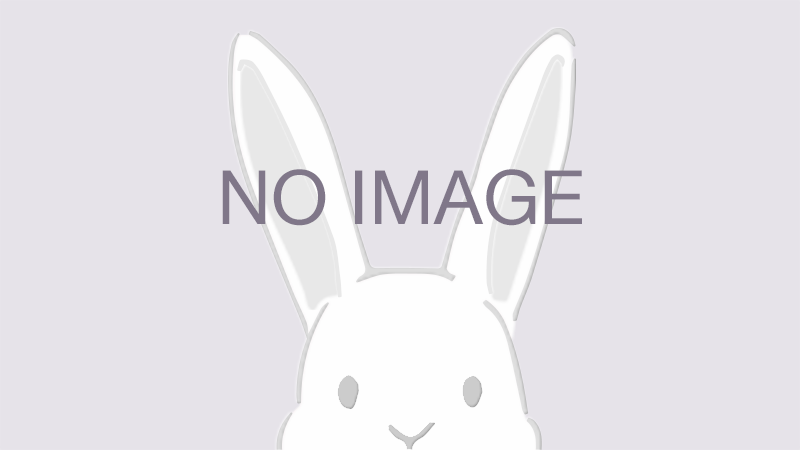


コメント