本多勝一著、朝日文庫、2019年11月22日に読み始め、12月16日に読了しました。
『PYON’S HONG KONG』の原稿執筆に取り掛かる前に、読み直したいと思ったのです。初めて読んだのは2003年8月4日~12月12日で、会社で配られたからでした。改めて読んでみてたいへん勉強になり、同僚にプレゼントしました(記事はこちら)。とくに第三章「修飾の順序」と第四章「句読点のうちかた」は目から鱗が落ちる思いがしました。繰り返し読んで、血肉にしたいと思います。
p9~11 (略)また例文として小説から引用することもあるが、それはあくまで「作文の技術」のためであって、決して「小説の技術」のためではない。言葉の芸術としての文学は、作文技術的センスの世界とは全く次元を異にする〔注1〕。その意味での「事実的」あるいは「実用的」な文章のための作文技術を考えるにさいして、目的はただひとつ、読む側にとってわかりやすい文章を書くこと、これだけである。
実はこうした文章論に類するものを書くことに、私はいささかの躊躇と羞恥をおぼえざるをえない。というのは、私自身が特にすぐれた文章を書いているわけではないし、もちろん「名文家」でもないからだ。それに、私のごく身近な周辺、つまり今つとめている新聞社の内部にさえ、私など及びもつかぬ名文家や、技術的にも立派な文章を書く人がたくさんいる。いわゆる年代的な「先輩」ではなしに、純粋に文章そのものから見ての大先輩に当たるそうした人々をさしおいて、この種のテーマを書きつづることの気はずかしさを、読者も理解していただきたい。にもかかわらず書くのは、開きなおって言うなら、むしろヘタだからこそなのだ。もともとヘタだった。うまくなりたいと思いつづけてきた。中学生のころを考えてみても、同級生に本当にうまい文章を書く友人がいた。とてもかなわないと思った。はからずも新聞記者となってすでに十数年、もはや「名文」や「うまい文章」を書くことは、ほとんどあきらめた。あれは一種の才能だ。それが自分にはないのだ。しかしこれまで努力してきて、あるていどそれが実現したと思っているのは、文章をわかりやすくすることである。これは才能というより技術の問題だ。技術は学習と伝達が可能なものである。飛行機を製造する方法は、おぼえさえすればだれにでもできる。発明したのはたまたまアメリカ人だが、学習すればフランス人でもタンザニア人でもエスキモーでも作れる。同様に「わかりやすい文章」も、技術である以上にだれにも学習可能なはずだ。そのような「技術」としての作文を、これから論じてみよう。
p17 日本語の作文を日本人が勉強することも、このような外国語作文の原則と少しも変わらない。私たちは日本人だから日本語の作文も当然できると考えやすく、とくに勉強する必要がないと思いがちである。しかしすでに先の実例でもわかる通り、書くことによって意思の疎通をはかるためには、そのための技術を習得しなければならない。決して「話すように」「見た通りに」書くわけにはいかない。イギリス語作文でコンマをどこにうつかを考えると全く同様に、日本語作文では読点をどこにうつべきかを考えなければならない。
p18 要するに一つの建築みたいにして作りあげるのである。建築技術と同じような意味での「技術」なのだ。なんだか大げさで、えらいことのようだけれど、作文は技術だからこそまた訓練によってだれでもができるともいえよう。
p245 全く単純な第一歩は、少なくとも終わりまで読んでくれるものを書くことだ。最後までとにかく読まれなければ話にならない。途中で放りだされてはとうてい目的を達せられない。文章をわかりやすくするための技術をこれまで論じてきたのも、ひとつにはこのためだといえよう。
p262 特殊な分野の専門家とか観念の遊戯が好きな高等遊民的知識人などは別として、一般の人は遠い世界のことよりも身近なことに、自分に関係の薄いことよりも直接関係あることに、抽象的なことよりも具体的なことに高い関心を抱いている。文章によって他人に訴えるとき、これは留意すべき重要な原則といえよう。つまり同じ内容を訴えるなら、できるだけ関心のより高いものを材料にすべきだ。そのためには、できるだけ身近なこと、できるだけ読み手に直接関係のあること、できるだけ具体的なことをとりいれてゆく必要がある。
p266 職業がら私も多くの新聞記者と接し、その書くものを読んできて思うに、読ませる文章を書く記者は、ほとんど例外なく、たいへんよく取材し、かつ作文技術のすぐれた人だ。自分自身の体験で考えてみても、どこか説得力に欠けた部分があるとき、必ずといってよいほどそれは取材不足の部分であった。具体的材料が足りないと、どうしても筆先でカバーしようとする。そうすると具体的事実によらず、観念や理論や説教がナマのかたちで出てきやすく、それらが先行すればするほど説得力を欠き、ウサン臭いものになってゆく。
p268 具体的に書くためには、程度の差こそあれ取材活動が必要だということが、以上で納得できると思う。したがって文章を書くということは、実際に机でペンを持つ以前の、手足を使ってのまめな動きをも含んだ実践的作業だということもできる。もちろんその中には、図書館での文献調査や新聞のキリヌキといった作業も含まれよう。
p271 つまり、一般の人はセミの穴を見てもその表層構造しか考えない。ファーブルは同じ穴を見ながら深層構造まで示してみせたのだ。似たようなことは、原子物理学であれ微生物学であれ有機化学であれ、自然科学上の大発見にはいくらでもある。どうしてそれが人文科学や社会科学にないといえようか。文章の世界も全く同様である。
p299 (略)さらにその後の経験から考えると、大学ノートのページは全巻の通し番号とするよりも、一冊ごとに別ページにしておいて、たとえば3冊目の18ページなら「3-18に関連」という書き方をする方がラクだし、あとでページをさがすのにも速い。
→このノートの使い方は参考になりました。ツイッターで気に入ったツイートをノートに書いているのですが、そのノートが増えてきて困っていたところ、解決策が見つかりました。早速実践してみました(写真)。
先述した、同僚にプレゼントしたのは新版だったのですが、きっとパソコンの使いこなし方が載っていると思うので、購入したくなりました。
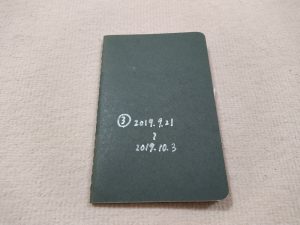
(解説より)
p340~341 想いがあふれるときはかえって文が乱れる。堰を切ったように、節が、句が、詞があふれてくる。当人にとってはおもしろいかもしれないが、他人にとっては傍迷惑となる文章がこうして生まれる。
文章は、ひとの迷惑になってはいけない。
ひとの迷惑とならないためには、読者の立場にたって、自分の文章を読みかえし、訂正し、よりわかりやすくすることが肝心である。達意ーーこの金文字こそ、わかりよい文章を書く人に与えられる勲章である。
本多氏の「忠告」を守っていれば、ひとはおのずと、達意に近づくことができよう。
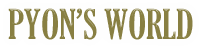
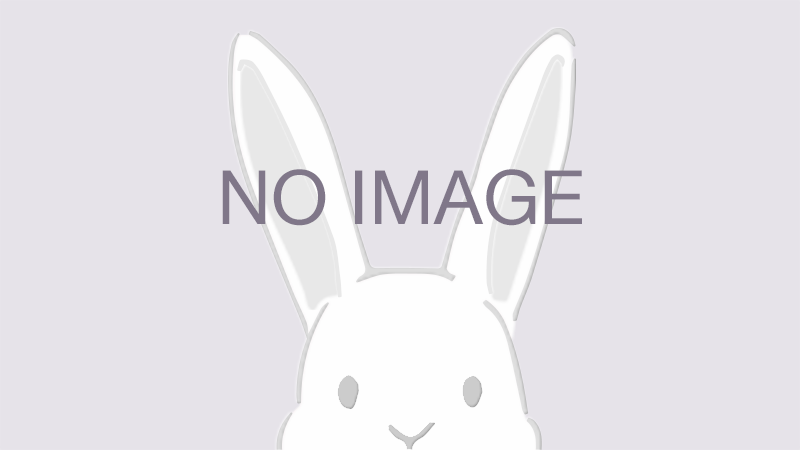


コメント