ジョン・デューイ著、市村尚久訳、講談社学術文庫、6月19日に読み始めて10月1日に読了しました。
p104 子どもには、いま一つの本能がある。それは、紙と鉛筆を使うということである。子どもというものはすべて、形と色という媒介をとおして、自己を表現することが好きである。
p117 子どもはいつでも語るべき何かを、言おうとする何かを心にもっているのである。そのことはまた、子どもが表現すべき思想をもつということである。思想というものは、それが自分自身のものでなければ、思想に値しないのである。
p124 すなわち、教養とは想像力の成長ということであり、それが柔軟性に富み、見通しをもち、共感感情をもつことができるような方向へと成長し、ついには、一人ひとり個人が営む生活が、自然や社会での生活によって満たされるような、そのような想像力の成長のことをいうのである。
p149 芸術は、思想と表現手段との生きた結合にほかならない。この結合を象徴的に表現するならば、この理想の学校においては、芸術作業というものは、いろいろな作業室でおこなわれている作業が、図書室および博物室という蒸留器をとおされて、再び行動になったものと考えることができる、ということになるだろう。
p261〜262 何事によらず、理論上に根本的な相違がある場合には、その違いをもたらすだけの理由があり、その理由は決して根拠のないものでも、捏造されたものでもない。その相違は、問題にするに足るだけの正真正銘の問題自体のなかで、しかも葛藤状態にある諸要因のなかから生起してくるのである。その真正の問題とは、それら問題の要因をあるがままに取りあげると、その問題を生起させている要因が相互に衝突し合っているというまさにそのゆえに、その問題は本物の問題であるということになるのである。どのようなものでも意義深い問題というものには、当面しばらくは、相互に矛盾するような条件が含意されているものである。その問題を解き明かすということは、すでに固定されている用語の意味にこだわることから脱却して、いま一つ別の観点から、つまり、新しい光に照らして、条件を見直すようになることによってのみもたらされるのである。しかしながら、このように問題解決のために条件を再構築することは、とりもなおさず、新しく思想を生み出すための陣痛を意味することになる。既成の考え方を放棄し、また、すでに学ばれ知られている事実から離脱して、新たに思考するということよりは、すでにいわれていることを固守し、そのことに対して反撃されないようにと、むしろそれを支持するだけのなんらかの理由を探し出そうとして、まさにその既存の言説を墨守することの方が、はるかに安易なやり方である。
p262 教育的過程を構成するうえで、基本となる要因は、未成熟で未発達な存在というものであり、さらにまた、成人の成熟した経験のなかに体現されているある一定の社会目的・意味・価値といったものである。その教育的過程には、これら未成熟と成熟が有する効力による相互作用が当然のこととして起こってくるのであるが、まさに、教育的過程とは、それら成熟と未成熟という両者による作用にほかならない。最も十全で自由な相互作用を促進するうえで、一方のものと他方のものとが相互に関係し合うという概念こそ、教育理論というものの本質にほかならないのである。
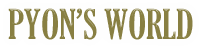
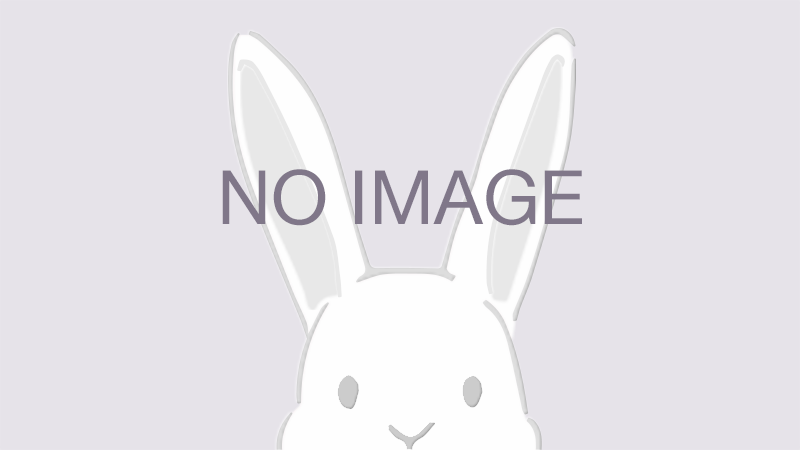


コメント